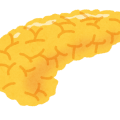「糖尿病とはどんな病気ですか」
糖尿病とは持続的に高血糖が続く病気です。ただ、糖尿病と一口にいっても、さまざまな原因で起こることが報告され、検査により分類されています。
糖尿病とはどのような病気かと、聞かれたら、多くの皆さんが生活習慣病のイメージをおもちです。
体質(遺伝)の要素もあり、いちがいに生活習慣が悪いとレッテルを貼るのは問題があります。
糖尿病の原因の一つが食べ物の過剰摂取の影響が考えられる場合もありますが、原因が体質の要素が強い場合もあります。
一方で、どのタイプの糖尿病でも、治療の際には、食事療法(あるいは、食事に配慮すること)が有効となりますので、生活習慣に多少なりとも気を付けることが必要です。
糖尿病の分類は成因からはおおきく3つに分けられています。(日本糖尿病学会 糖尿病診断基準に関する調査検討委員会より改変)
1)1型糖尿病
膵ベータ細胞の破壊、通常は絶対的なインスリン欠乏(インスリン不足)に至る病態と定義されます。
自己免疫性(1A)と特発性(1B)に分類されます。
ゆっくりインスリン欠乏状態になる緩徐進行1型糖尿病、1ヶ月から数ヶ月くらいで発症が判明する急性発症1型糖尿病、多くの場合、1週間以内でインスリン欠乏になる劇症1型糖尿病と
進行のスピードでの分類もあります。
1型糖尿病の原因がストレスではないかと心配される患者さんもいらっしゃいます。
ストレスが原因というよりは、ストレスが糖尿病の状態を悪化させる因子になる可能性はあります。
2)2型糖尿病
インスリン分泌の低下が主体のものと、インスリン抵抗性が主体で、それにインスリンの相対的不足を伴うものがあります。
インスリン分泌の低下の具合やインスリンの効きの悪さの具合は個人差が大きいです。
そして、肥満合併の2型糖尿病患者さんはインスリン抵抗性が高い場合が多いです。
すなわち、インスリン分泌はしっかりしているが、インスリンの効きが悪い状態を指します。
2型糖尿病の原因がストレスというよりは、ストレスの影響でお菓子などの糖質の過剰摂取が原因の一つになる場合があります。
糖尿病の原因が不明な場合は、いったん2型糖尿病として、治療され、他の病型の可能性がないか、絶えず見直すことになります。
3)その他の特定の機序、疾患によるもの
A)遺伝子異常
膵ベータ細胞機能に関する遺伝子異常
インスリン作用の伝達機構に関わる遺伝子異常
治療方法は、インスリンの効きの良さ、インスリン分泌の具合で決定されます。
B)他の疾患、条件に伴うもの
膵外分泌疾患、内分泌疾患(甲状腺機能亢進症やクッシング病などの内分泌ホルモンの過剰が原因となる)、肝疾患、薬剤や化学物質によるもの
感染症
免疫機序によるまれな病態
その他の遺伝症候群で糖尿病を伴うことが多いもの
一見、2型糖尿病に見える患者さんでも、膵癌が隠れていたりする場合があり、病型の決定には注意を要する場合があります。
4)妊娠糖尿病
妊娠中の糖代謝異常で明らかな糖尿病を合併していない状態を指します。
糖尿病に至っていない段階の軽い糖代謝異常でも妊娠時は厳重に管理する必要があります。
■ワンポイントアドバイス
詳細な問診、診察、検査から分類します。
どのタイプか知ることで、治療に役立つ場合と、現時点ではあまり役立たない場合がありますので、患者さんと相談の上、鑑別を進めていきます。
インスリン分泌が枯渇している場合や低下している場合は、一時的かずっとかは不明な場合がありますが、インスリン治療が必須になる場合があります。