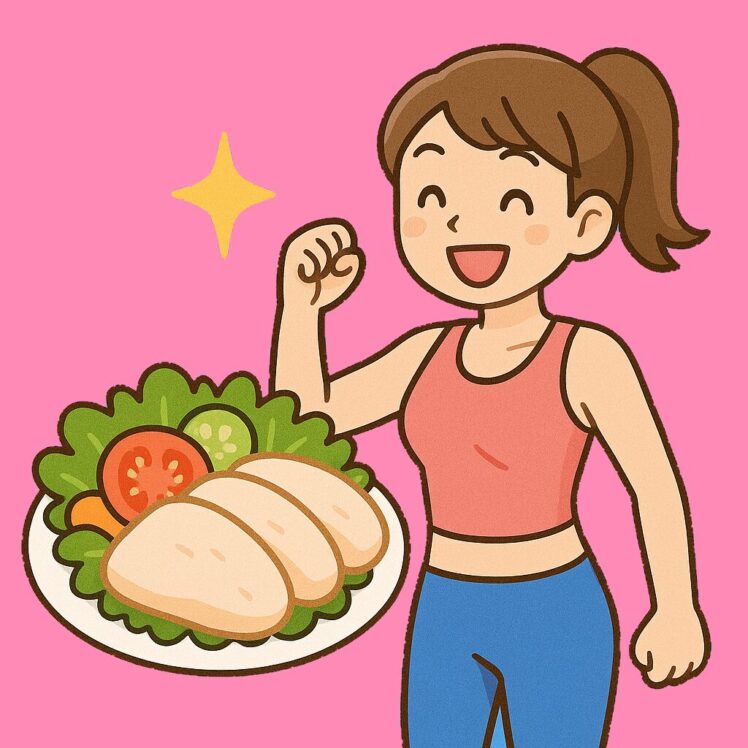 食べ物の話
食べ物の話 サラダチキンでダイエット🌟血糖値を下げる効果も!
スーパーだけでなくコンビニでも目にする機会が多いサラダチキン!皆さんは、食べたことありますか?サラダチキンって筋トレをしている人が食べているイメージ!鶏肉だけだし、パサパサしていて美味しくないでしょ?そんな風に思っている方もいると思います!...
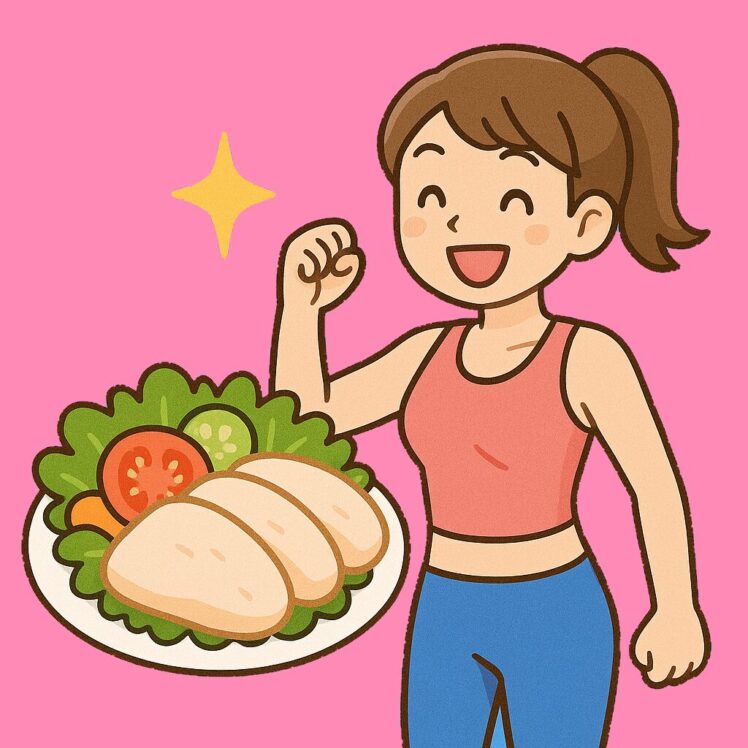 食べ物の話
食べ物の話 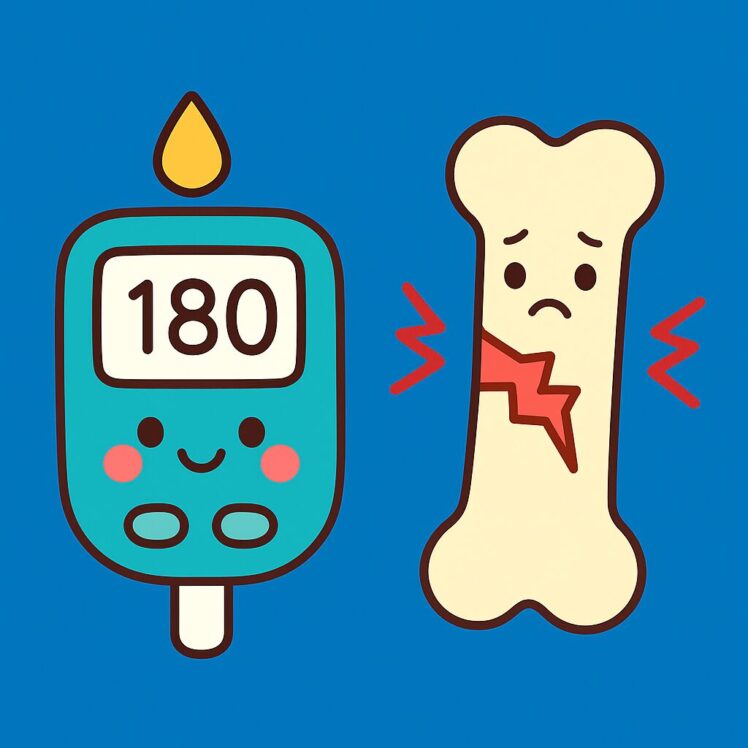 栄養素の話
栄養素の話  食べ物の話
食べ物の話  食べ物の話
食べ物の話 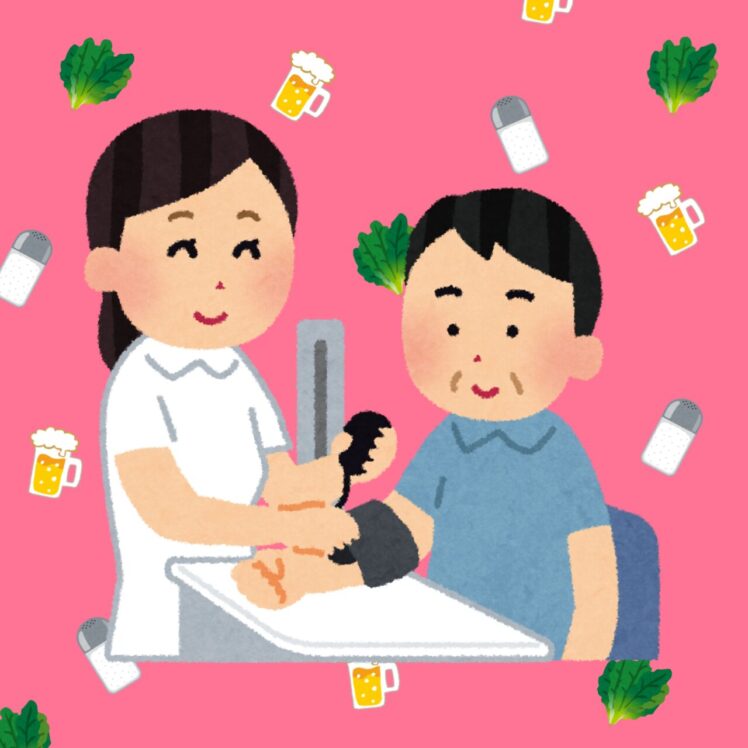 栄養バランス
栄養バランス  栄養バランス
栄養バランス  食べ方の工夫
食べ方の工夫 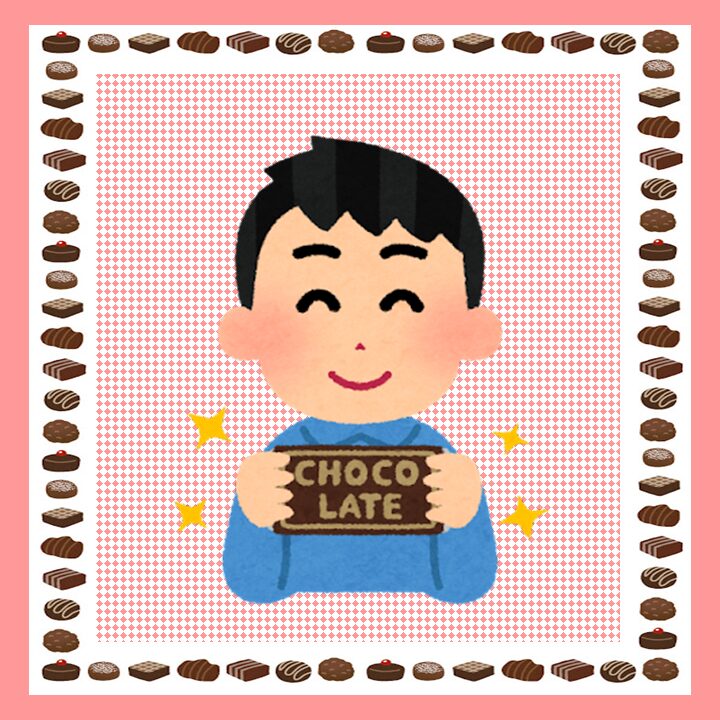 食べ物の話
食べ物の話 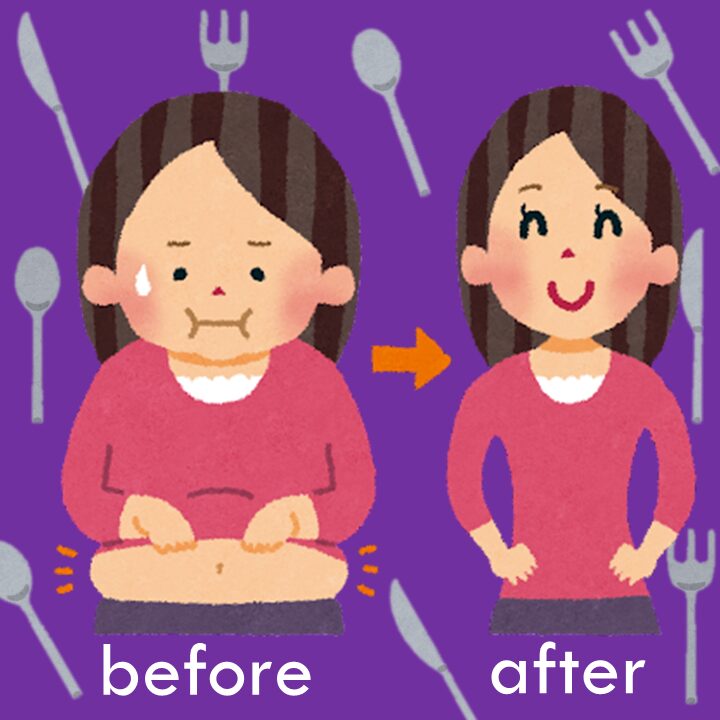 食べ物の話
食べ物の話  食べ方の工夫
食べ方の工夫  栄養素の話
栄養素の話  食べ方の工夫
食べ方の工夫  食べ物の話
食べ物の話  生活習慣
生活習慣